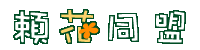『花見て跳ねるは月夜のうさぎ』
最後のうさぎは、ちらりと花梨のほうをふりむき、ぴくぴくと耳を動かした。
「…かっ、かわいい…!」
思わず目を潤ませたのは花梨だ。
彼女、かわいいものには目がないのである。
「餌の礼を言っているのかもしれません」
むしろ、うさぎを見て子供のように喜ぶ花梨に笑みを誘われながら頼忠は言った。うさぎは大きな目をぱちりとひとつまばたかせて、草むらの中へと消えていった。
どうもこのあたりにはうさぎの巣があるらしく、可愛らしい姿に出くわすことが多い。いつのまにやらうさぎのための餌を持ち歩き、食べさせるのも花梨の日課だ。
怨霊の浄化はもちろん、その地の力を強めたり、困っている人を助けたり、あげくは野良猫野良犬野良うさぎの餌やりまで、神子の日常は多忙を極めている。
消えていったうさぎたちの後を目で追いかけながら花梨は少しばかりさびしそうに溜息をついた。
「だけどやっぱり野生のコは触らせてくれないなあ…」
「神子殿は、うさぎに触れたいのですか?」
問う頼忠に、花梨はふにゃりとした笑顔を向ける。
「うーん、やっぱり撫でてみたいっていうか………。ほら、ふわふわして可愛いし」
「お望みなら、捕らえてまいりましょうか?」
真顔である。
思わずコケそうになった花梨は。
「だめだめだめっ! そんなことしたら余計におびえるじゃないですかっ」
声を荒げた。
ややあってしゃがんでいた花梨は立ち上がる。
「それじゃあ、今度は呪詛探しですね」
「はい」
頼忠の口元も引き締まった。
幸鷹の情報によると、ここ何日か和仁親王がこのあたりによく訪れているのだという。見ての通り何もない場所に親王が人目をしのんでくるなど明らかにおかしい。
これまでも和仁はそうやって呪詛の種をばらまいていたので、今回も懲りずに凶行に及んだと考えてまず間違いはないだろう。
「問題はどんな呪詛か………なんだけど」
「神子殿は何も感じませんか?」
頼忠に花梨はこっくりとうなずく。
どうも和仁の呪詛は、微弱すぎて特定するのが難しいのだ。
であるがゆえに、被害もさほど深刻を要するものではない。だからといって放っておくこともできないので訪れたのだが。
「…そのあたり、ちょっと探してみましょうか」
ひとりごちた花梨は、とりあえず人の踏み込まなさそうな茂みの辺りに行こうとする。
「神子殿、おひとりでは !?」
その後を追おうとした頼忠の視界の端に。
「………?」
うさぎがいた。
一瞬、さきほどのうさぎかと思ったが、それは頼忠の前でにっと笑って見せたのだ。
「っ?」
その笑みがあまりにも邪悪だったので頼忠は反射的に太刀を握る。
だが、それ以上体は動かなかった。
「うーん、ないなあ」
ごそごそと茂みから戻ってきた花梨は、頭に枯葉を絡ませている。
「ねえ頼忠さん、そっちはど……………ってアレ?」
戻ってくると頼忠の姿はない。
「よ、頼忠さん!? どこ!?」
思わずきょろきょろとあたりを見回すがやはり人影はない。そのかわりに、花梨の目に飛び込んできたのは、藍色の着物と鯉口が切られて数寸ほど鞘から出た刃だった。
「うそ…っ」
思わず駆け寄って見れば、上着だけではない。靴も袴も小袖も手甲も、頼忠が身に着けていたものがまるまるそこにあるではないか。
まるで本人だけが蒸発してしまったかのように。
「………そんな………」
呪詛の影響だろうか。しかしいくらなんでもあの頼忠が何も言わずに消えるなどおかしい。
もう一度、頼忠の名前を呼びかけたその瞬間。
………。
どろりとした気配が背後に忍び寄った。
「ッ!?」
反射的に身をかわせば、そこには怨霊がいる。一瞬、子供と見まごうような容姿だが、口は耳まで裂け、そこからはぎらぎらと刃のごとき牙が覗いている。決して大きなものではないがその凶暴さは、一目で分かる。
「う、うそ………」
青ざめながら花梨が後ずさるや否や。
奇声を発した怨霊が花梨に向かって飛びかかる。
思わず観念して両目を閉じるが、不思議なことに怨霊の牙は花梨には届かなかった。
「えええっ?」
そして素っ頓狂な声を上げてしまうのも無理はない。どこからともなく現れた野性のうさぎが、小さな怨霊にさらに小さな身で体当たりをしていたのだ。
「ギィッ!」
いくら小さな怨霊といっても、うさぎが太刀打ちできる相手ではない。あっというまに胴体をつかまれる。怨霊の指には、いやに長く尖った爪が光っていた。
怨霊は、その暴れるうさぎを口元に持って行こうとする。
「だっ、ダメ!」
叫んだのは花梨だ。
そして彼女は反射的に頼忠の太刀を握っていた。
「そのコを離しなさい…ッ!」
ほとんど何も考えずに太刀を手に突進するが、とっさのことに怨霊は何もできない。ただ次の瞬間には、頼忠の太刀は怨霊の胸のあたりに深々と突き立っていた。
おそらく大した怨霊ではなかったのだろう。たったの一撃で、おどろしい声を上げながら霧散してしまった。
「………」
花梨はというと突然の怨霊の襲来やら、はじめて握った太刀の重さや、肉を突く感触にすっかり気おされてその場に腰を落としてしまう。
すると。
ひくひくと鼻を動かしながら、白いうさぎが花梨の膝元に寄ってくる。何か物言いたげな赤い瞳には不安げな花梨が映っていた。
「おまえ、私のこと助けてくれたの…?」
問いながら花梨が手を伸ばすと、ぴくりと耳を動かしたうさぎは逃げもせずにそこにいる。それどころか、花梨の無事を確かめるかのように花梨の膝のあたりに顔を近づけるくらいだ。
「………ふふっ」
思わず力なく笑った花梨はそのままうさぎを抱き上げた。
「くすぐったいな、もう」
言いながら、ふにふにとうさぎの顔を撫でると、ずいぶんおとなしく目を細めて花梨を見ている。
「ねえ、頼忠さん見なかったかな?」
問えばうさぎはぱちりとひとつ瞬きをするだけだ。
「………って答えてくれるワケないか………」
ひとりごちながら花梨は、ああどうしようと溜息をついた。
。
夜になっても頼忠は戻ってこなかった。
とりあえずそこにあった頼忠の衣服や太刀を持ち帰ってみたが、呪詛の片鱗を見つけることもできない。けれども、ここまで姿を見せないということは何かあったと見てまず間違いはないだろう。
「それで、こいつは?」
たまたま居合わせた勝真が、花梨の膝の上のうさぎを指す。
「怨霊に襲われたとき、このコが助けてくれたんです。もしも怪我をしてたらって思って連れて帰ったんですけど………」
でも怪我はないみたいで良かったね、と額を撫でる。うさぎは気持ちよさそうに耳を動かした。
「どれどれ?」
と、ひょいとうさぎをつかんだのは勝真だ。
「お、コイツ、オスだぜ?」
「ちょっ、ちょっと…っ! 勝真さんっ」
ふいに猫掴みされたうさぎはキーキーと暴れている。
「なんか、めちゃくちゃ怒ってるんだけど………?」
いまだに勝真の手の中で暴れるうさぎを覗き込んで花梨が呟く。
「男は嫌いみたいだな………」
勝真も呆れ顔だ。
「そうじゃなくて、勝真さんの扱いが悪いんですよ」
そして花梨はひったくるようにうさぎを救出する。花梨の手の中に戻っても、うさぎは勝真を睨み付けていた。
そんな視線をものともせずに勝真は。
「それで、本当に頼忠は消えたのか?」
「………」
花梨はしょんぼりとうつむく。確かにうさぎは可愛いが、頼忠の不在は一大事だ。力の弱い怨霊ならばどうにか退けることができても、彼の力なしに戦うことは決してたやすくはない。
「まぁ、そう気ィ落とすな」
ぽんと勝真は花梨の頭を撫でた。
「明日になったら、泰継や幸鷹も手伝うって言ってるし、すぐに見つかるだろ」
いやあいつのことだ、動けるようになれば夜明けを待たずに帰ってくるかもなと笑う。
「…神子様、」
声をかけたのは紫である。
「湯をお使いになられませんか? 今日は泥だらけにおなりでしたし………」
「え、本当に? うれしい」
確かに怨霊との戦いでいささか汚れていたのだ。他にも色々と気疲れしている花梨を慮ってわざわざ用意してくれたのだろう。
「あ、じゃあ、紫姫………、このコも一緒に入っていい?」
花梨が抱き上げたのはうさぎである。
腕の中でうさぎは何度か目をしばたたいたようであるが、紫は「まあ」と笑って口元に手をあてる。
「もちろんかまいませんわ。ご一緒にきれいにしてあげてくださいませ」
くすくすと笑って告げた。紫にしても、ふわふわのうさぎは可愛らしくて仕方がないらしい。
そんな和やかな様子をほほえましげに眺めた勝真は。
「じゃあ、俺もそろそろ失礼する。また明日な」
「あ、うん。わざわざありがとうございました」
。
夜の森の中、和仁は不遜な笑みを浮かべた。
「どうやら………呪詛はうまく働いたようだな」
「………」
時朝は無言で和仁の後ろに従っている。
和仁は続けた。
「このあたりのうさぎは飢えていた。その空腹感を怨みに変えるように仕向けたのが功を奏した。間違いなく、あの忌々しい彰紋の周りの誰かは力を喪っているはずだぞ」
「………は」
時朝は小さくそう呟いただけだった。
そしてふと、茂みからこちらを覗いているうさぎに気がつく。
和仁はうさぎには気付かぬ様子だ。
どうせなら彰紋に呪詛が行けばよかったものをとぼやいている。
覗いたうさぎは、ひくひくと小鼻を動かしてから、ぴょんと茂みの中に消えた。
「………」
はて、と時朝は思案する。
今のうさぎは、どう見ても空腹に耐えかねている様子ではなかった。それどころか何かを怨むようなそぶりは一切見せない。
しかし和仁はどうやらご満悦のようだし、口にすることでもないだろう。
うさぎがあの様子ならば、おそらく呪詛はそれほど甚大な被害はもたらすまい。そこまで考えて、時朝は小さく胸を撫で下ろした。
。
「はああ、」
ちゃぷんと花梨は大きな盥(たらい)の中で溜息をついた。
うさぎは、最初はじたばたと暴れたものの、花梨に抱かれて湯につかる頃にはすっかりおとなしくなっていた。
「本当にどこ行っちゃったんだろう………」
呟きながらうさぎの頬の辺りを撫でると、ひくりと動いた耳が湯を弾いた。
うさぎは相変わらず、何か言いたげな瞳で花梨を見ている。
「ん? そっか、おまえは頼忠さんのこと知らないもんね」
ひとつ笑った花梨は、ぽつりぽつりと語り始めた。
「 でね、一緒に院を助けようってことになったの」
不思議なことに、うさぎはおとなしく花梨の声に耳を傾けている。
「頼忠さんはいつも怪我ばっかりしながら、でも私のことを必ず守ってくれるの。どんなときでも、気がつけば頼忠さんは私のそばにいたの、」
そして、いつの間にか頼忠の後ろにいることで怨霊が怖くなくなっていた。
どんなことがあっても、頼忠は常に花梨を守ってくれた。その頼忠に、自分はいつも惹かれていた。
「私ね、まだ自分にそんな力があるなんて信じられない………。でも、もしあの人のためにできることがあるなら………この都を守れるなら、そうしたい」
あるいはこれは、とても利己的な理由なのかもしれない。自分が守りたいのは都ではなく、頼忠が住む場所なのだ。
頼忠がいなければ、自分は今頃どうしていただろう。
そして頼忠がこのまま帰ってこなければ、自分はいったいどうなってしまうだろう。
じわりとにじんだ眼から、ぽつりと涙が落ちた。
ぴくりとうさぎは耳を動かす。
「っ、だから………」
ぎゅ、と抱き締めた小動物の体は、とても優しくて柔らかかった。
「私、頼忠さんがいたからここまで来れたの………だから、」
震える声は湯気に溶ける。
「早く…、早く、帰ってきてよ………」
小刻みに震える肩に、うさぎはそっとあごを摺り寄せた。
。
「………月か、」
帰路につく勝真の頭上、晴れた空の上で月が輝いている。通りで明るいはずだ。
この月は、都中を照らしている。
すべからく闇を照破する月の光は、ともすれば神子の浄化の光のようだ。
そして勝真は呟いた。
「明日はいい天気になりそうだな」
。
「きれいな月」
ぼんやりと花梨は呟いた。
いつものように濡れ縁の手すりに腰をかけて夜を見上げる花梨の膝には、洗ってもらっていっそうふかふかになったうさぎがいる。
「神子様、」
深まる秋の夜は決して暖かいものではない。心配した紫が声をかける。
「せっかく、湯を使われたのに………また冷えてしまいますわ」
「うん…でも、なんだか、中に引っ込んでられなくて」
花梨は背中のまま告げる。
「でしたらせめて、これをおかけくださいませ」
そう言って紫が差し出したのはいつもの袿(うちぎ)ではない。頼忠の上着だ。
「…頼忠殿が、早く戻ってまいりますように」
紫は優しく微笑んだ。
「……………うん」
厚手の藍の上着には、血埃の匂いが染み付いていた。
けれどもそれは、暖かかった。
じわじわと夜が明けてゆく。
いつの間にか眠っていた花梨の腕の中でひょこりと身を起こしたうさぎは、消えてゆく月を見た。
すると、溶けるようにうさぎの姿が変わり始める。
「ッッ!?」
そして月が朝の色に消えると同時に、頼忠は起き上がった。
白々と明けてゆく空の下、眠る花梨の頬にはくっきりと涙のあとが残っている。
「 神子殿、」
呟いた頼忠は花梨の涙のあとを指でなぞった。
抱き起こされた気配にぼんやりと花梨が目を開ければ、くぐる御簾と武士の姿が見えた。花梨の肩には頼忠の上着がかけられたままで、花梨を抱きかかえる頼忠は小袖姿だ。
「………」
しばらく、花梨は朦朧とする意識に惑う。
そして。
「よっ、頼忠さん!?」
にわかに大声を上げた。
「神子殿、夜明けにはまだ間がありますゆえ、どうぞ中へ」
頼忠はいつもと変わらぬ様子だ。
「えっ? えっ? い、いつ戻ったんですか??」
花梨は目を丸くしている。すると頼忠は申し訳ありませんと詫びた。
「不覚にも………呪詛に囚われておりました」
「怪我は? 痛いところとか………」
「ご安心を」
どうやら五体は満足らしい。怪我をした様子もない。
「………よかったー」
本当に心底ほっとしたというように胸を撫で下ろす花梨に、頼忠は再度心配をかけたことを詫びる。そして、安心したところではっと花梨はうさぎのことを思い出す。
「そ、そうだ、あのコ………っ、」
しかし見回せどもあのうさぎの姿はない。
「ねえ、頼忠さん、うさぎ見なかった? 真っ白のコなんだけど………」
「そ…っ、それは………っ、」
ふとあわてたそぶりを見せたのは頼忠だ。一瞬、言葉をなくすが。
「あのうさぎは………どうやら野に帰ったものと………」
「ええっ?」
花梨は心底残念そうな顔になる。
「せっかく仲良くなれたのに…、名前も考えてたのに………」
「も、申し訳ございません」
頼忠はなぜか謝る。そして。
「あのうさぎにも、帰る場所があるのでしょう………」
「…うん、そうですね」
残念そうにしながらも、花梨は微笑んだ。
「それにまた、ご飯持って行ったら会えるもんね」
「………はい」
そして頼忠はひたりと花梨を見た。
「神子殿、」
「??」
あまりにも真剣な瞳に、花梨は一瞬気圧される。
「このたびは不覚をとりましたが………必ず、神子殿のおそばにおります」
真摯な瞳が花梨を映している。
「どんなときでも、必ず、私がお守りいたしますゆえ………どうか、ご安心を」
「あ、う、…うん」
とたんに頬に朱を覚え、惑うようにうつむきながら上目に頼忠を見れば。
「………」
真摯な…けれど物言いたげな瞳が。
「あ、あれっ?」
その瞳が、あのうさぎを髣髴とさせて花梨は頓狂な声を上げる。
「よ、より…っ、まさか………」
言いかけて、はたと気付く。
あのうさぎは頼忠だったのではないか………。そう思いはしたが、よくよく考えてみれば自分はあのうさぎと風呂に入った上に、本人にはとてもとても語れないようなことをべらべらとしゃべったわけで。
「あ、………う、ううん、やっぱり、なんでもない」
早口に打ち消す。
しかしあわてふためく心臓と赤面は止まらない。
「………ご心配をおかけして申し訳ありません」
頼忠はあくまでいつもと同じ態度だ。
「あ、う、うん、でも無事だったし、うん。良かったです! あ、そうだ。みんなで明日は頼忠さん探そうってことになってるから、ちゃんと、謝らないと………ね」
すっかり目の覚めた花梨は、心のわだかまりを打ち消すように無理やりに笑顔を作った。